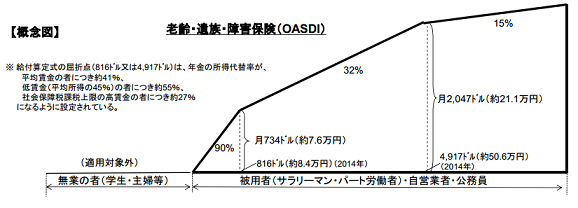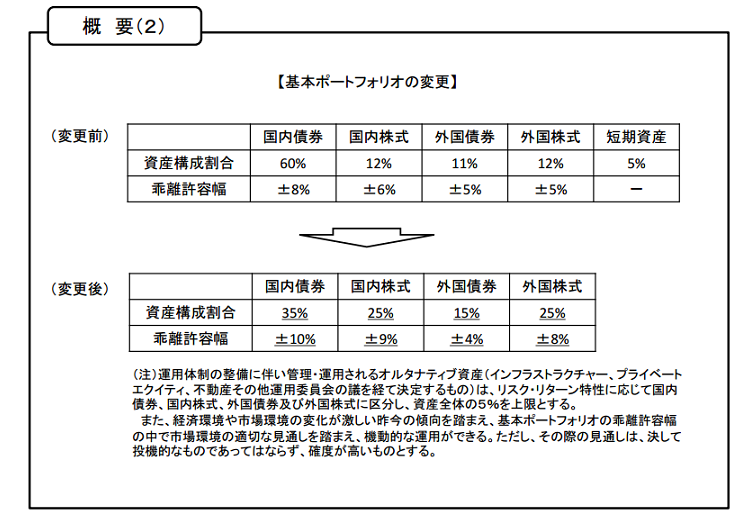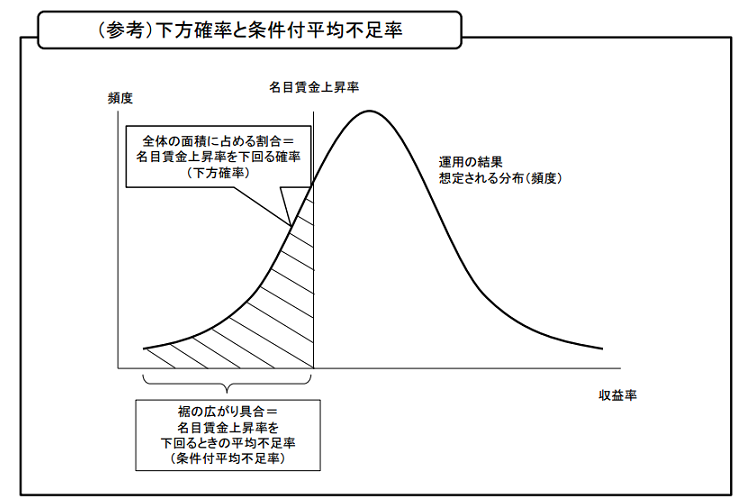インドのモディ新首相が海外で最初に訪問先に選んだ国が日本になった事で話題になっており天皇陛下もお会いになった事がニュースにも取り上げられております。安倍首相と交わした共同宣言でも、日本は3兆円規模の投資を行い拠点数を2倍に増やすとなっておりますが、実はインドは日本企業の拠点数のランクでは昨年実績で中国、アメリカについで第3位になっております。
- 中国 拠点数 31661拠点
- アメリカ 拠点数 7193拠点
- インド 拠点数 2510拠点
ちなみに 第4位はアジアのデトロイトと言われているタイで1580拠点となっております。 それだけ拠点数の多いインドですので、さぞかし多くの日本人赴任者がすでに赴任していると想像できますが、赴任者数の統計では驚くほど少なくなっています。 民間企業からの海外赴任者ランキングは以下の通りで
- 中国 赴任者本人 75246名 赴任者家族 32268名 帯同人数比率 43%
- アメリカ 赴任者本人 54742名 赴任者家族 10209名 帯同人数比率 109%
- タイ 赴任者本人 27341名 赴任者家族 16703名 帯同人数比率 61%
- シンガポール 赴任者本人 11912名 赴任者家族 11772名 帯同人数比率 98%
- イギリス 赴任者本人 9343名 赴任者家族 10209名 帯同人数比率 109%
- ドイツ 赴任者本人 7149名 赴任者家族 7199名 帯同人数比率 101%
かなり順位を下げて インド 赴任者本人 4102名 赴任者家族 1833名 帯同人数比率 45% となっております。
人口12億人の巨大な市場でその国土も広く、かつ地域地域での独特な合弁相手先と州ごとに異なる税金制度があるインドでは、現地でのビジネスをするためには拠点数は必要だがまだまだ日本あるいは日本人にとっては遠い存在の国がインドと言った感じがします。 私自身、前職で海外赴任者に関係する仕事をしておりましたが、その際に気にしていたのが帯同率で赴任者本人にご家族が一緒に赴任しているか(帯同しているか)の割合です。
外務省の統計では家族数としては統計が取られていませんが、家族一人ひとりを人数に数えた帯同人数の統計はあり、それで比較すると上のリストの通りインドは45%と非常に低くなっております。欧米では、1人の赴任者に奥様(配偶者)とお子様が何人か帯同され帯同人数比率が100%を超えることが多くなっておりますが、インドの場合はかなり低いのが現状で、単身赴任が多くなっているあるいはご結婚されていない独身赴任者が多くなっていることが推測できます。
今回のモディ首相の訪日を機に、インド側での税制面その他での改善がなされ、日本企業が進出しやすい環境が整い、インドへのご家族を含めた赴任者が増え、相互の交流が深まる事を願いたいと思います。具体的には、日本と世界各国(現在15か国)との間で発効しております社会保障協定があります。インドとの間でもすでに社会保障協定は締結しておりますが、まだ発効はされておりません。これを機に早期に発効され相互の人材の移動についての制約が削減されてゆくことも期待したいと思います。
社会保険労務士事務所プラムアンドアップルでは、海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。